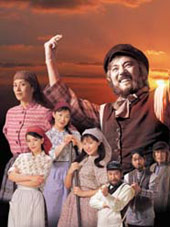
屋根の上のヴァイオリン弾き
原作=ショラム・アレイヘム
台本=ジョセフ・スタイン
音楽=ジェリー・ボック
作詞=シェルドン・ハーニック
演出=寺崎秀臣
ルビ吉観劇記録=2001年(東京) 2004年(名古屋)
|
|
【この芝居について】
1964年にブロードウェイで初演。日本では1967年に開幕以来、幾度となく上演を繰り返しており、今回の公演期間中に1200回目を迎える人気演目。主人公のテヴィエは長らく森繁久彌が務めたのち、西田敏行が二代目として引き継ぐ。今回はキャスト、演出も一新されたニュー・バージョン。三代目テヴィエには市村正親が選ばれた。
スタンダード・ナンバーとしてもお馴染みの「サンセット・サンライズ(日は昇り又沈む)」は、このミュージカル最大のヒット曲。
|
【物語】
帝政ロシアの寒村、アナテフカ。ここに伝統(しきたり)を大切に守りながら暮らしているユダヤ人たちの集落があった。テヴィエはここで酪農を営み、貧しいながらもよく働き、信心深く暮らしている。妻のゴールデには頭が上がらない恐妻家であるが、5人の娘たちが可愛くてしようがなく家族を何より愛している。
政情が徐々に悪化しロシア政府によるユダヤ人弾圧が進む中、ちょうど年頃を迎えた3人の娘たちに、次々と結婚の話が持ち上がる。この村での結婚は、仲人と親が決めた相手と結ばれるのが“しきたり”となっている。しかし3人の娘たちは、そのしきたりを次々と破り、伝統の枠から外へと飛び出して行く。長女のツァイテルは周囲の反対を押し切り、恋仲だった貧乏な仕立屋と結婚。次女のホーデルは愛する革命家を追いかけるため、家族を捨てシベリアへ行ってしまう。そして三女のチャバは、よりによって自分たちユダヤを弾圧するロシア人と駆落ち。
伝統を守りつつも、新しい世代の考えも受け入れざるを得ないテヴィエ。一方では悪化して行く政情が、否応なくテヴィエたちユダヤの民を飲み込みはじめ…。
|
【観劇記】
以前に観た西田敏行さんのバージョンと、似て非なる舞台でありました。西田さんの『屋根の上…』は明らかに“お涙ちょうだい”的なマッタリ感があったのですが、新バージョンは軽快。「今日は思いっきり泣くぞ!」と張り切って出かけた俺などは、少し拍子抜けなところもありました。でも正直、どちらもアリだし、同じ物語でも演出、キャストでこうも違うから、芝居って面白いんだとあらためて思います。
西田さんのテヴィエと市村さんのテヴィエは別人(とは言い過ぎ?)。ほんわかした西田さんと、シャープな感じの市村さんでは、単に風貌だけ比べても全然違いますからね。でも市村さんは華がありすぎ…とも思いました。華と言うより個性と言った方が適切でしょうか。芝居全体の中でどうも市村さんだけが突出しているんですよ。演技も上手い人だから、泣かせるところ笑わせるところのメリハリも効いていて、他の役者さんたちとは全然違う。もちろん歌も上手いし、踊れる。上手い芝居を見せてもらって文句を言うな!って話ですが(笑)、市村さんのひとり芝居の感がなきにしもあらず…。西田バージョンの時は、他にも大勢の個性的俳優たちが主役を取り囲んでいたようにも思い出されます。
それでも他の出演者で際立って良かったのは、テヴィエの妻ゴールデを演じた夏木
マリさん。テヴィエが恐妻家となるだけの、なかなかたくましいオカンを演じててイメージ通り(笑)。年格好も市村さんと近く、わかりやすい夫婦感がナイス・キャスティング。
娘たちは今回あまり期待していませんでしたが、次女の知念里奈、三女の笹本玲奈は歌が良かった。特に三女の笹本さんは、俺は『イーストウィックの魔女たち』に続いて二度目だったんですが、今回は若々しくもしっかりとした演技にも魅力を感じました。
3人の娘たちと結婚をする男たちは更に期待していなかったのですが、こちらは俺的には全員ハズレ。芝居はそこそこ悪くないんですが、歌がいただけない。そしてナンと言っても老けすぎ。新郎には見えませんって!もっともそれを言い出すと、長女役の
香寿たつきの「新婦」「花嫁さん」ってのもキツイものがあるんですが(笑)。
舞台装置は前回よりもスッキリとした印象。今回は東京、名古屋以外は旅公演が基本となる作品だけに、かなりシンプル。オーケストラなどもオケピのないホールでの上演を可能にするためか舞台上に。それらは観ていて何ら不都合のないものでしたが、すっきりシンプルな舞台を実現するならチケット代もシンプルにせぇよ!とはセコイ話でしょうか?(笑)
|