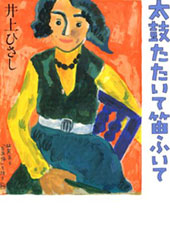
こまつ座 第72回公演
太鼓たたいて笛ふいて
原作=井上ひさし
演出=栗山民也
音楽=宇野誠一郎
ルビ吉観劇記録=2004年(神戸)
※右は戯曲の表紙。
|
|
【この芝居について】
『紙屋町さくらホテル』同様、井上ひさしを座付き作家に持つ“こまつ座”の芝居。初演は2002年7月。物語は『放浪記』を発表してから47歳で亡くなるまでの、林芙美子の半生を描いたもの。初演、そして再演にあたる今回も主人公・林芙美子は大竹しのぶが努めている。
初演の評価はすこぶる高く、この舞台の演技で大竹しのぶが第10回読売演劇大賞と同最優秀女優賞を受賞、木場勝己が同最優秀男優賞、こまつ座が同最優秀作品賞を受賞。また同じくこの演技などで大竹しのぶが第37回紀伊國屋演劇賞、第2回朝日舞台芸術賞を受賞。井上ひさしが『太鼓たたいて笛ふいて』の戯曲で第6回鶴屋南北戯曲賞、この戯曲など一連の作品で第44回毎日芸術賞を受賞−−−という輝かしい記録。
|
【物語】
林芙美子が『放浪記』を発表したのが、昭和5年。舞台はその5年後の昭和10年から始まり、彼女が亡くなる昭和26年までを描く。
『放浪記』がベストセラーとなり、たちまち国民の人気者となった芙美子。しかしその後は出版物が発禁処分を受けるなどパッとしない。勝気な芙美子は悶々としていた。そんな折、ラジオ局のプロデューサー・三木から「先生は世の中をわかっていない。今、世の中は“戦争は儲かる”という理屈で動いている。その理屈を頭に入れて物語を書けば発禁処分など受けないし、本は売れる」と煽られる。日清戦争では莫大な賠償金を手に入れ、日露戦争では旅順、大連、南樺太を手に入れ、第一次世界大戦では景気がよくなった。戦争は儲かる。そのために日本は勝たねばならない。つまりそういう話を美しく表現すれば本は売れるというのだ。
日中戦争が始まった昭和12年。芙美子は従軍文士として、また女性では初めて、陥落後の南京に出征する。そこで見たもの聞いたものを国民に伝える芙美子。たちまち芙美子は国民の人気を得る。
昭和20年3月。芙美子が疎開先で「こうなったら(日本は)キレイに負けるしかないでしょう」と発言したことが問題となる。三木たちは「先生はどうしちゃったのか?!」と疑問に思う。芙美子をよく理解するこま子は「先生が変わってしまわれたのは、南方戦線で
何かを見たから」だと言う。
やがて日本は終戦。終戦後、芙美子はとりつかれたように、次々と新作を発表。
芙美子は一体何を見て何を感じ、戦後に何をどう考えていたのか…?
|
【観劇記】
この『太鼓たたいて笛ふいて』は戯曲で読んだだけでも、本当に面白く、また感動的。ところが芝居となると大竹しのぶという適役を得たことで、面白さも感動も何倍にも膨れ上がった。大竹さん、本当に芝居が上手い!先日は“森光子、『放浪記』で林芙美子を演じて1700回!”というニュースが報じられました。森さんは昭和36年以来43年間も
芙美子を演じてきたそうですが、大竹さんにも頑張って長く芙美子を演じ続けて欲しいものです。
俺の中で林芙美子に関する知識などあまりありませんでした。『放浪記』を書いた作家。「私は宿命的な放浪者である。私は古里を持たない。したがって旅が古里であった」という、有名な『放浪記』の書き出しそのままの人生を送った女性。その程度の認識でした。まさかこれほど戦争色の強い人生を送っていたとは驚きです。もし戯曲が事実に忠実であるのならば、林芙美子は「太鼓たたいて笛吹いて」戦争をはやし立てた。そして自らその罪を問い、自らその罪を償う。これを“潔い”と言うのかどうかはわかりませんが、俺は彼女の生き様にひたすら感動してしまいました。
それにしても俺は思うのです。ミュージカル『李香蘭』を観たときも同じことを考えましたが、一個人が担う戦争責任ってなんだろう?どこまでが罪なのか?戦後に生まれて戦後の教育を受けた者は、戦後の理屈を以って当時の罪や責任なんて語れない。国家のそれは明々白々とそこに存在しても、一国民となると…。と、まぁ、そんなことも考えてしまう芝居でした。
話は舞台に戻って−。こまつ座の芝居は音楽を多用した演出が多いのですが、この演目では歌を歌う場が、なんと10箇所以上あります。しかも半分くらいはオリジナル曲(残り半分は詞のみオリジナル。曲は既成曲)。ミュージカルではなく音楽劇では「おいおい、何故こんな場で突然歌うんだ?!」と感じるものもあるんですが、これは歌の入り方が自然。また、歌によってはフリが付けてあるものもあり、ちょっとしたミュージカルのようでもありました。
6人の出演者はみんな、とても歌えそうにない役者ばかりなんですが、今回はそれが逆に身近な感じをかもし出していて効果的だと思いました。ちなみに大竹しのぶさんの歌は上手くもないんですが、独特の歌唱法で聞き入ってしまいます。キャラクター同様歌でも不思議感の高い(?)女優でした。
******************************************************************
余談ですが、もう何年も前に尾道へ出張で行った際に林芙美子が10代の大半を過ごしたという旧居を訪ねたことがあります。旧居は「芙美子」という喫茶店の奥にあって、見学したい人はその喫茶店を利用しなければならない。文化財の見学にしては珍しいというかちゃっかりしているというか(笑)。
ところで訪れた年の夏は深刻な水不足が中四国地方を襲った時で、飲食店は営業もままならい悲惨な状態。それでも芙美子ゆかりの喫茶店は、洗う水がないから紙コップでコーヒーを出すも、たいへん繁盛しておりました。今思えば、芙美子がのり移ったようなたくましい営業だったよなぁ、と懐かしく思い出されます。
|