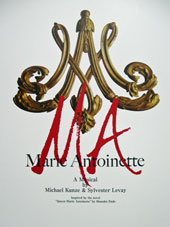
マリー・アントワネット
脚本・歌詞:ミヒャエル・クンツェ
音楽:シルヴェスター・リーヴァイ
演出:栗山民也
ルビ吉観劇記録=2006年(東京)
|
|
【このミュージカルについて】
遠藤周作の同名小説『マリー・アントワ・ネット』を原作とし、『エリザベート』『モーツァルト!』を手がけたミヒャエル・クンツェとシルヴェスター・リーヴァイが初演をウイーンではなく、東京発で発表したミュージカル。 |
【物語】
18世紀後半のパリ。人々は飢えと貧困に苦しむ日々を送っていた。その中のひとり、孤児のマルグリット・アルノーは、ある日宮廷の舞踏会に潜り込む。彼女がそこで見たものは、輝くばかりの王妃・マリー・アントワネットであった。思わず「貧しい者たちを助けて」と王妃に懇願するも、嘲笑で返されてしまう。
ノートルダム寺院前の広場では、マルグリットの恩人ラパン夫人の公開鞭打ち刑が執行されていた。売春宿の経営に対して王妃自身が下した処分だという。恩人を救えなかったマルグリットは怒りと悔しさから、貧困のない自由を求めて闘おうと民衆に呼びかけるのであった。そんな折、かの有名な“首飾り事件”が起きる。高額な首飾りが王妃の名を偽って購入され、しかも行方知らずになってしまった事件だ。身に覚えのない王妃は「これは策略だ」とばかり、関与した者を逮捕。その中にはマルグリットもいた。
裁判の結果、釈放されたマルグリット。しかし彼女の王妃に対する憎悪は頂点に達し、「倒すべきはマリー・アントワネットだ」と民衆に呼びかける。マルグリットにとって母のようなシスター、アニエスは走り過ぎる彼女を憂い「人が人を傷つけることで世の中は何も変わらない」と諭すが聞く耳を持たない。
貧困に耐えられないパリの民衆は立ち上がり、やがてフランス革命が勃発。ルイ16世、マリー・アントワネットたち王室一家はベルサイユを追われ、国外逃亡も失敗しタンブル塔に幽閉される。そしてマルグリットは召使という名のもと、見張りとして王妃のもとにやって来る。しかし王妃や皇太子たちと暮らすうち、マルグリットは自分の中の何かが変わり始める。
やがて王妃の審理が始まり、マルグリットは証言台に立ちありのままの真実を話す。しかしそれを無視するかのように、王妃はありもしない非人道的な罪まで負わされてしまう。そしてマルグリットの中の信念も崩れ始めていくのであった…。
|
【観劇記】
ハッキリ言って、満足感の得られないミュージカルであった。期待し過ぎたのであろうか。良かった悪かったと語る以前に、制作意図がわからないのだ。いずれにしても観客の感情の流れを無視した作りとなっていると思った。
主役の二人・マリーとマルグリットは社会の究極の上と下にそれぞれいて、極端に言えば双方共に人の心が欠けている。それが立場が変わることで人間的な成長を遂げるという構図が物語にはあるようなのだが、起承転結の起と結だけ描かれている感がある。変化の過程が断片的にしか描かれていないのだ。それゆえ理屈で物語を理解しても、感情を揺さぶられることはない。
また革命の描き方も中途半端。“民衆が理不尽な社会を倒して自由を勝ち取る”といった、革命を希望に溢れたものとして見せないことは新鮮に思った。革命は結局多くの人々の命を奪うだけで、それにより本当に幸せな社会を築けるのか?という問題提起を製作者はしたいのかなぁ…程度のメッセージも感じた。しかしそれも後で頭で無理やり考えて感じたことである。
そのほかにも登場人物の設定にも疑問。狂言回しと思われる、物語の本筋に関係ない役が三人も登場する必要があるのか?しかも主役クラスの役者を配役しているため三人の存在感も大きく、ストーリーを余計に複雑にさせているとしか思えない。
と、まぁ、書き出したらキリがないのだが、何が描きたかったのだろう?と客に思わさせるミュージカルはいかがなものか。脚本家も演出家もプログラムや雑誌のインタビューではもっともらしいことを語っているが、観劇後にあらためて読むと彼らのマスターベーションにしか感じないのである。観劇後、ネットで自分と同じ素人意見を検索すると出るわ出るわの悪評。多かれ少なかれ言ってることは同じ。またプロの批評家の意見にも目を通すと、皆さん遠慮勝ちながらも似たようなことを書いている。製作者たちはこれらの意見をどう受け止めているのだろう。すごく知りたい。
感想の大筋としては以上の通りだが、音楽は感動的な楽曲が数曲用意されている。また役者たちはそれぞれに魅力的。マリー・アントワネット役の涼風真世は華やかだし、マルグリット役の新妻聖子は迫力ある歌唱で憤りを表現した。アニエス役・土居裕子の歌の上手さは言うまでもないが、今回はマルグリットを諭す母としての役割を歌で見事に表現していた。
気になったのは、美しいながらもシンプルな舞台美術。物語がわかりやすい時は、セットにシーンの説明をしてもらう必要がないのでこんなのもアリ。しかし今回は違うだろう。それと“世界初演!ワールドプレミアム”とまで謳う大作ならではの、わかりやすい豪華さも個人的には欲しいところであった。
|